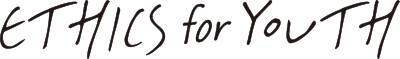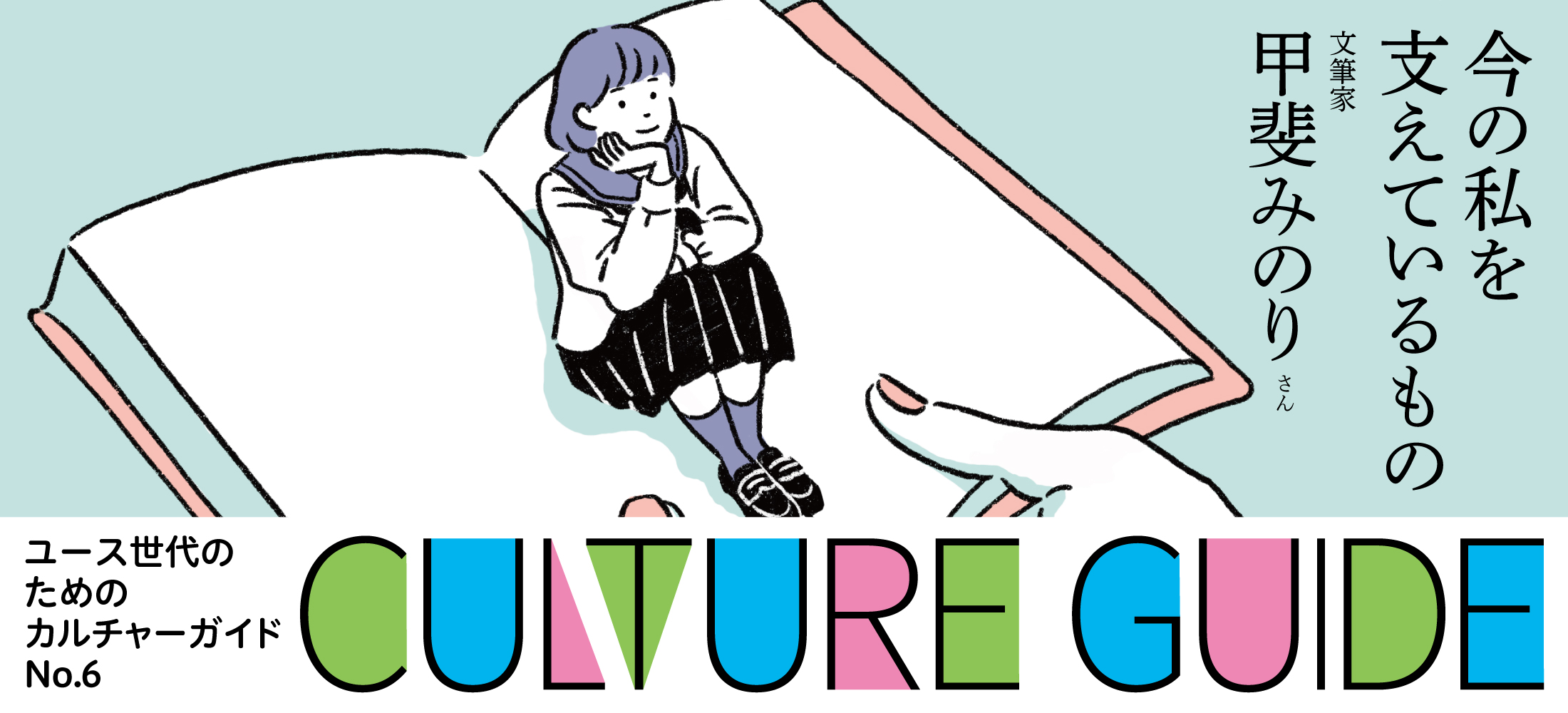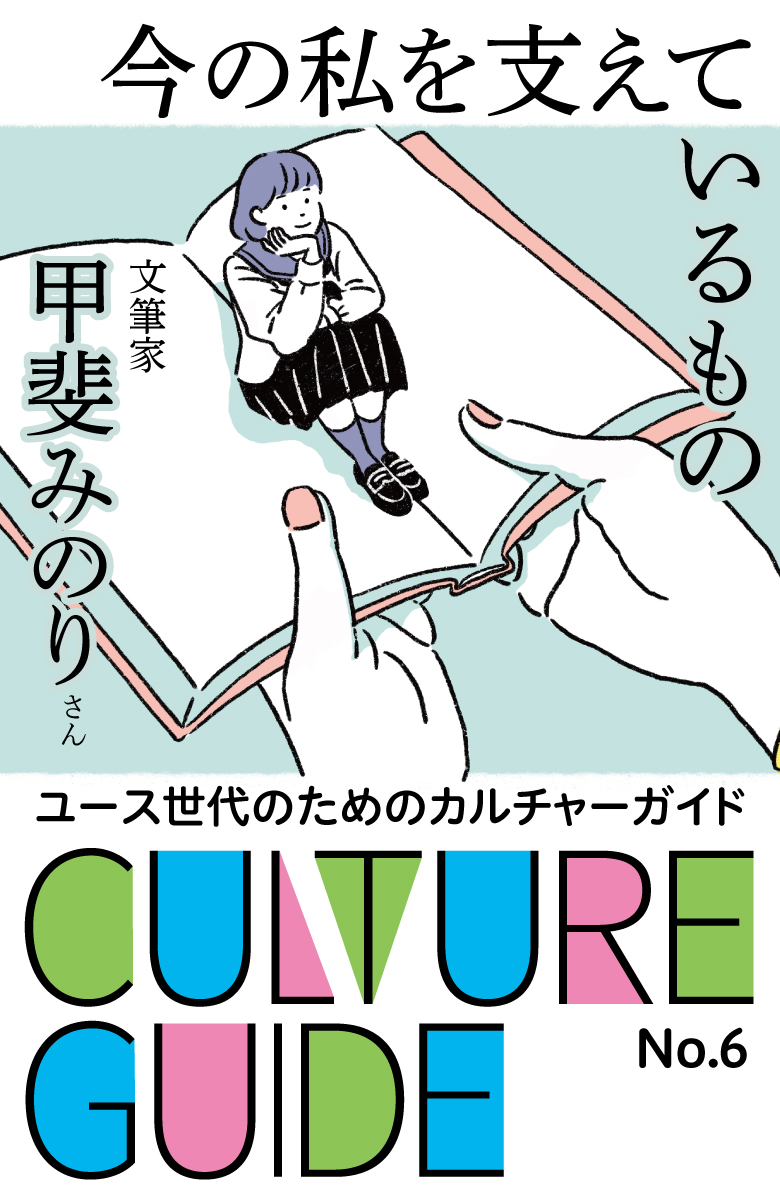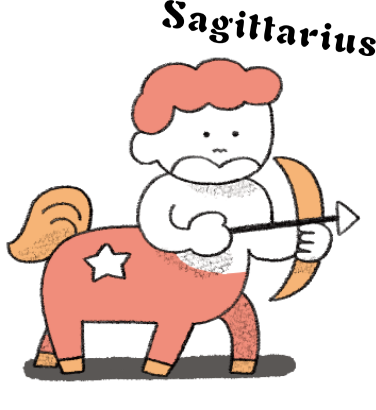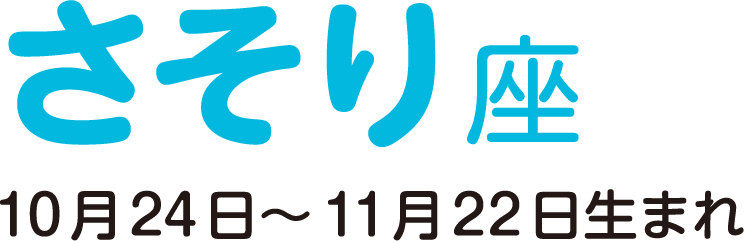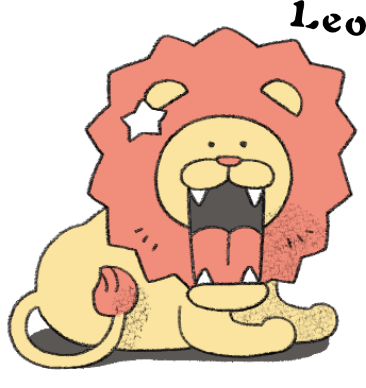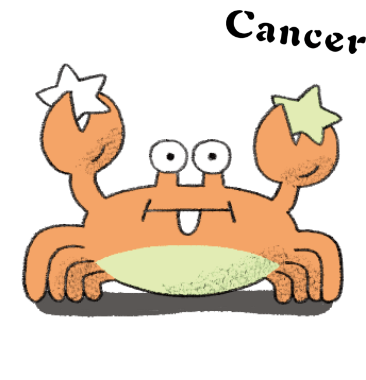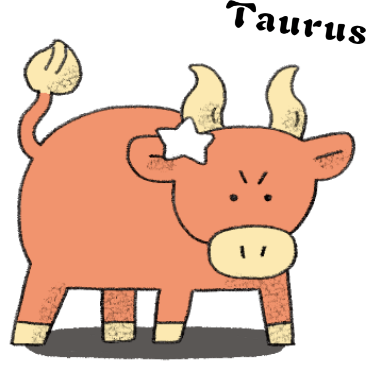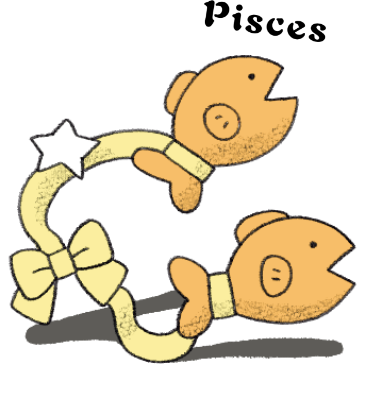父も母も俳人(俳句を作る人)という家庭で育った。小学生の頃は休日にお弁当を持って家族で野山に出かけ、季節の情景を歌に詠む両親の隣で、ひたすら本を読んで過ごした。クラスメイトが、ディズニーランドに連れて行ってもらったとか、流行りのゲームを買ってもらったと話すのがうらやましくて、“私も”とせがんでも、「うちはうち、よそはよそ。自分で稼ぐようになったら思う存分、やりたいことをやって、買いたいものを買えばいい」と言われるばかり。そのためか、大人になること、働くことへの憧れが、人一倍強かったように思う。それでも「本だけはいくらでも買ってあげる」と、読書へ向かう扉はいつでも開かれていた。そうして小学生の頃から、いつか本に携わる仕事がしたいと夢を抱いた。
13歳で『Olive』という雑誌に出合った。そこには、吉本ばなな、酒井順子、秋元康などによる「文章講座」の特集が組まれていたり、小沢健二と小山田圭吾が組んでいたバンド、フリッパーズ・ギターや、シャルロット・ゲンズブール主演のフランス映画『なまいきシャルロット』が紹介されていたり。ファッションだけではない、渋谷や原宿やフランスを軸に発信されるカルチャー情報に感化され、文芸・音楽・映画などの文化・芸術をもっと知りたいと欲求が募り、芸術大学への進学を決意した。
大学生になり、古本屋通いに夢中になっていたところ、ある店で「うちでアルバイトをしませんか」と声をかけられた。毎日、好きな本に触れられるのは願ってもないことだ。古い本だらけの空間で、店の掃除、本の汚れを落とし、値付けをおこない、レジを打つ。ただそれだけでも、いつか関わりたい本作りに近づいている気がして嬉しかった。働く喜びに満たされた。
鶴谷香央理の漫画『メタモルフォーゼの縁側』は、17歳の女子高生・うららと、75歳の老婦人・雪が、ボーイズラブ漫画という共通の“すき”をきっかけに心を通わせるストーリー。初めての創作に着手するうららに雪は、漫画を描くのは楽しいかと尋ねる。うららの答えは、“あんまり楽しくはない。でも、やるべきことをやっている感じがして悪くない”。
あんなにも望んでいた大人になり、物書きという職業に就いた今、うららの言葉が胸に響く。働くことは決して楽しさだけでは続かない。ましてや創作ともなれば、苦しみは避けられない。それでも、生き甲斐を探りながら仕事に勤しみ、半分自由(自分で稼いで使い道を選択できる)で、半分不自由(いつも締め切りに追われている)な、すべきことに溢れた毎日に、愛おしさを覚えている。

『メタモルフォーゼの縁側』
鶴谷香央理
(KADOKAWA)
最近、千葉俊二『作家たちの17歳』という本を読んだ。太宰治や宮沢賢治、文豪と呼ばれる人たちにも当然ながら17歳の頃があり、それぞれ“どう生きるか”苦悩や決断を抱えていたことが読み取れる。10代で明るく将来を見据え、順風満帆に歩むことなどそうはないことがよく分かる。しかしながら、考え、迷い、悩み、学び、試み、さまざまな体験を積み重ねることで、心の内が深く広く育つことも、作家たちの軌跡が物語っていた。
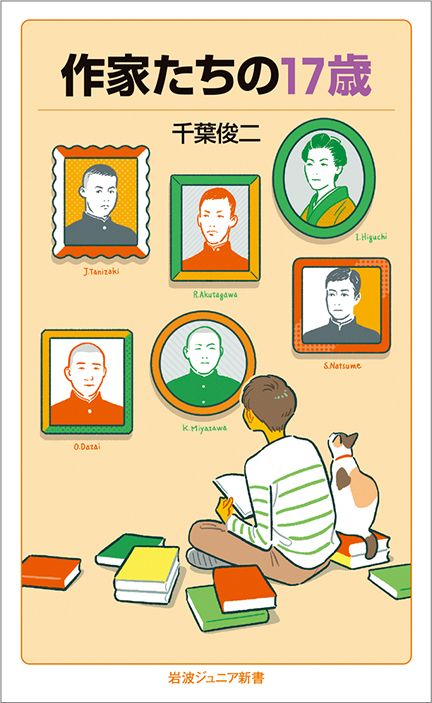
『作家たちの17歳』
千葉俊二
(岩波ジュニア新書)
振り返れば思春期の私は、他者と自分を比較してばかり。迷ったり、苛立ったり、うまくいかないことの多くを、家族や、環境や、なにかのせいにしていた。自分を育てるのも変えることも、結局は自分にしかできないと気がついた今、あの頃の私に伝えたいのが、『茨木のり子詩集』に収録されている「自分の感受性くらい」という詩。「自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ」二十代でこの詩を知ったとき、がつんと打ちのめされて、目が覚めた。以来、この詩はお守りのような存在だ。
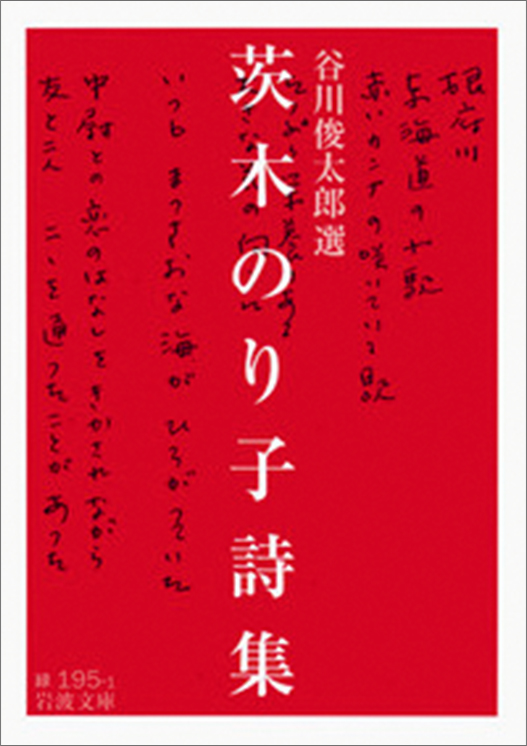
『茨木のり子詩集』
谷川俊太郎選
(岩波文庫)
自由を得るために働く。快く働くためにあらゆる経験を積み重ねる。働くことに憧れたあの頃の思いが、こうして今の自分を支えてくれている。

『「すきノート」のつくりかた』(PHP研究所)
甲斐 みのりさん
旅、散歩、手土産、パンやお菓子、クラシック建築、雑貨や暮らしなどを主な題材に、書籍・雑誌・webに執筆。自治体の観光案内冊子の監修や、講演活動も行う。著書は、ドラマ「名建築で昼食を」の原案にもなった『歩いて、食べる 東京のおいしい名建築さんぽ』や『日本全国地元パン』(共にエクスナレッジ)、『「すきノート」のつくりかた』(PHP研究所)『たべるたのしみ』『くらすたのしみ』(共にミルブックス)など50冊以上ある。

イラスト:くぼあやこ
※この記事は『ETHICS for YOUTH』2025年夏号(No.10)に掲載したものです。