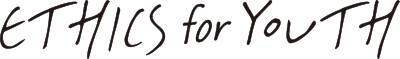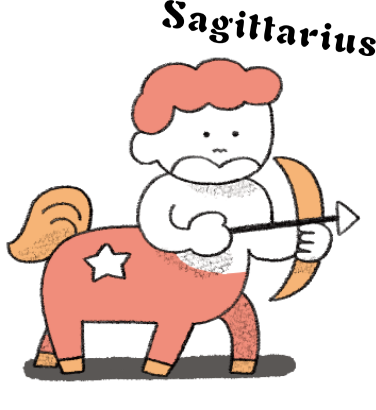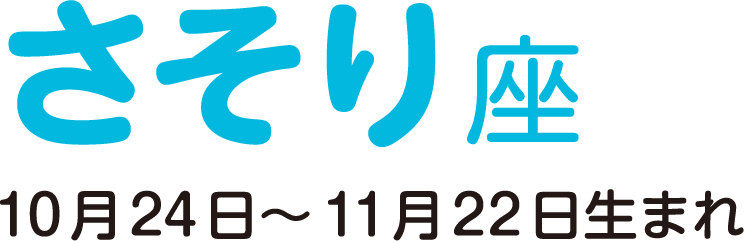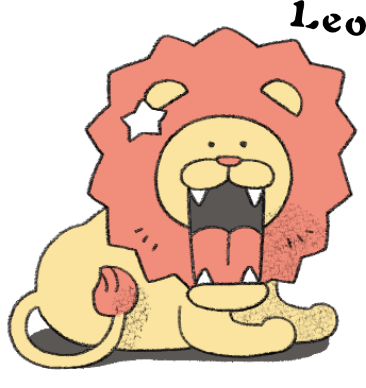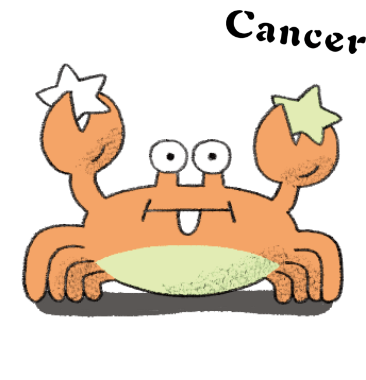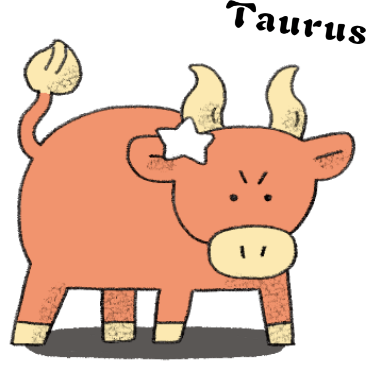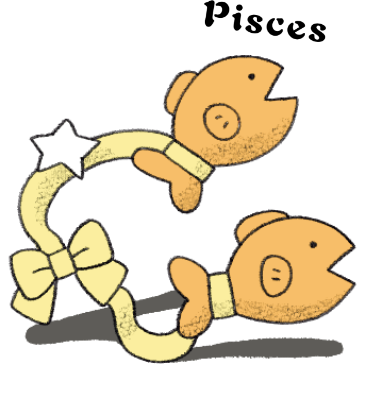「利他」という言葉を聞いたことがありますか?
辞書を開くと「利他」は「他人の利益になるように図ること」「自分より他人の幸福を願うこと」とあります。でも、具体的にどういうこと?
大学で利他について研究している中島岳志さんに聞きました。

「利己」という言葉があります。これは、自分のことだけを考えて行動すること。「利他」は、「利己」の反対語と思われています。でも、もしある人が「大学入試でアピールしたい」という理由でボランティアをしていたら、何か引っかかるものが残りませんか?それは利己主義的な利他行為といえるからです。誰かのためにしていることが実は自分のためだったり、自分のためだったのに結果的に誰かの役に立っていたり…。利他と利己は簡単には分けられない、メビウスの輪のようなものなのです。



じゃあ、どうすれば「利他」なのか。実は、私たちはもうたくさんの利他を受け取っているのに、それに気づいていないことも多いのです。例えば、太陽がもたらす光やあたたかさは、地球上のすべての生き物に恵みを与えてくれている。でも、改めて感謝することはありません。「何かをしてあげる」というより、私たちはすでに何かから「多くのものを受け取っている」。そう気づくことが、利他への第一歩になるのです。


電車でお年寄りに席を譲ろうとした時。「自分も疲れているのにどうしよう」「周りはどう思うかな」と、いろいろ迷ってから席を立っても、なんだか心がスッキリしません。でも、お年寄りを見たら反射的に「どうぞ」と動くと気持ちがいい。そうした行動には、計算や迷いがなく、相手からの見返りも期待していないからです。困っている人を見かけた時、何も考えずとっさに体が動くことが、利他の本来の姿だと思っています。
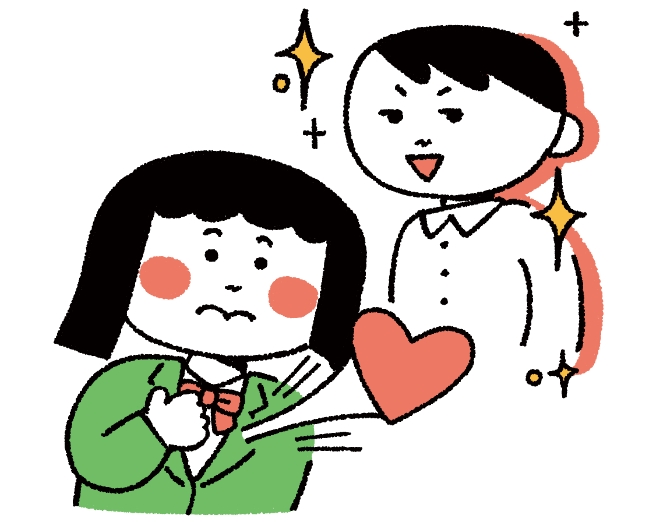

宇多田ヒカルさんは、ヒット曲「Automatic」で「側にいるだけで その目に見つめられるだけで ドキドキ止まらない」と歌っています。それは、ドキドキしようと思ってしているんじゃない。あなたといると勝手にドキドキしてしまうということ。恋って、頭で考えるよりも先に気持ちが動いてしまうものですよね。利他もこれと似ています。誰かのための利他的な行動は、自分の意思とは関係なく、自然と起こることが多いのです。

友だちにプレゼントをあげたり、悩みを聞いてアドバイスをしたり…。自分がよかれと思ってしたことが、相手にとっては「ありがた迷惑」になる場合もあります。大切なのは、利他は「与える側」でなく「受け取る側」によって決まるということ。受け取った人が「ありがたい」と感じた時に、初めて成り立つのです。「よいことをしよう」と頑張りすぎず、いま自分にできることをする。それが人のためになる、利他になるかもしれないのです。

大学の先生になって20年。たまに昔の教え子から「あの時の先生の言葉のおかげで人生が変わりました」と感謝されることがあります。でも、私は何を言ったのか覚えていません。特別いいことを言ったわけでもありません。日常の何気ないひと言を、教え子が心に留めて、大きく育ててくれたのです。このように、自分のさりげない言動が相手の力になれた時、そこで初めて利他が生まれたといえます。


「インドネシア」から「ネシア」を取ると?
「なぜインドの研究をしたんですか」とよく聞かれます。大阪外国語大学(現・大阪大学)のヒンディー語学科に入ったことがきっかけなのですが、なぜそこに入学したかというと、浪人中につきあっていた彼女が「大阪外語大に行きたい。インドネシア語の勉強したい」と言っていたから。
僕も同じ大学に行くことに決め、彼女に「じゃあ、俺もインドネシア語学科にしようかな」と言ったら、「定員が少ないのにやめて!」とすごく嫌がられてしまいました。仕方がないので、じゃあ「インドネシア」から「ネシア」を取って「インド」でいいやって。それが全ての始まりだったのです。
未来のためでなく「今」を生きよう
僕の大学に入学してくる学生の多くは、小学生の頃から塾に通い、家に帰ってきては学校の宿題をやって、寝て、また明日学校に行って……そんな日々を繰り返してきています。
親や塾の先生からは「あなたの将来のために、今は我慢して勉強しなさい」と言われる。では、大学生になったら遊べるかというとそうではなくて、今度は入学した瞬間から「自分のキャリアについて考えなさい」と促される。
「今」を生きているはずなのに、「今」が未来に支配されてしまっている。今の自分が消えて、本当の今の喜びが失われていく。そういうのってしんどい。
僕は、目標を持たないことにしています。日常生活でも、来たバスに乗ることにしています。いろいろと決めない方が、人生が意外な方向に流されていくからです。
僕に大切なインドを与えてくれたのも、たまたまインドネシア好きな彼女がいたから。 学生によく言うのは「大学生活を『未来への投資」と考えるな」ということです。今いる友だちとグダグダと1時間半しゃべっちゃったとか、そんなことが結構重要になってくる。目的に縛られる4年間じゃなくて、自由が与えられているのであれば、それに自分を開くことも大事だと思うんです。
再び「利他」の話
「文七元結」という落語があります。
長兵衛という男は、橋の上で、50両をなくして身投げしようとしている文七という青年に出会い、持っていた50両をあげてしまいます。その50両は、自分の娘が身売りをしないですむようにやっとの思いで借りたお金でした。
長兵衛はなぜ文七を助けてしまうのか。それは衝動なんです。川に飛び込もうとしている奴がいるのを見て、うわっ! と体が動いてしまう。50両をやってしまうんですよ。宇多田ヒカルの「Automatic」と同じ。この説明のできない行為というのが大切だし、「利他」の起点といえます。
みんなは、今の自分の恋は、自分にどんな利益になるのかとか、そういうことばかり考えているかもしれない。けれど、そんな未来なんて分からない。それよりも、その場で自分が果たすべきことを一生懸命にやることが、もしかしたら未来にとって利他的なことになるかもしれない。僕たちはその可能性を常に開いていくしかないと思っています。
(構成:編集部)
中島岳志

中島岳志さん
1975年大阪府生まれ。大阪外国語大学でヒンディー語を専攻する。京都大学大学院博士課程修了。東京科学大学リベラルアーツ研究教育院教授。現代日本政治や日本思想史、インド政治などを研究。著書に『思いがけず利他』『自分ごとの政治学』など。
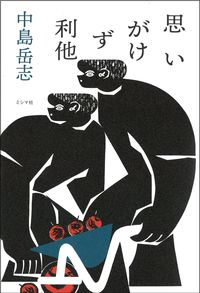
『思いがけず利他』
中島岳志(ミシマ社)
写真:中村嘉昭 イラスト:イラカアヅコ
※この記事は『ETHICS for YOUTH』2025年秋号(No.11)に掲載したものです。
JASRAC 出 2505897-501
※コラムはウェブオリジナルです。