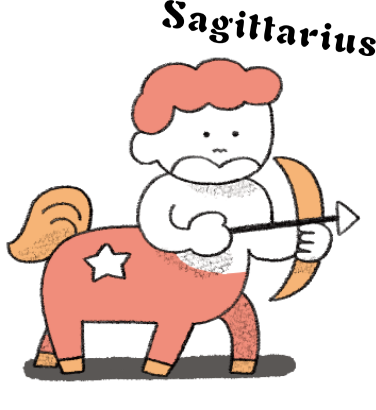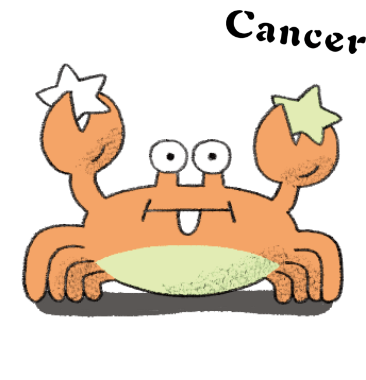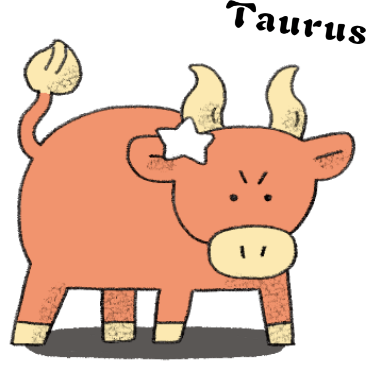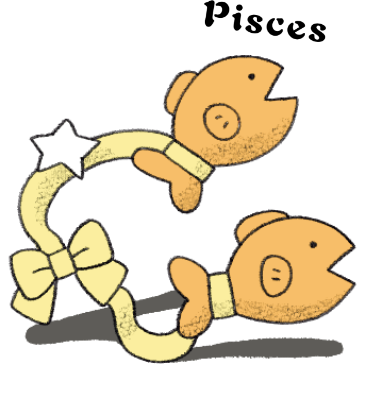“10代の頃の「なんとなく」に効いたフィクション”
10代の頃は、今以上にフィクションを、嘘を愛していた気がする。学校生活がもたらす圧倒的現実から遠くに逃げたくて、放課後はもちろん授業中ですら小説やマンガを読み漁っていた。べつに学校が嫌いだったというわけじゃない。仲のいい友人もいたし、楽しいこともたくさんあった。それでも、ふとした瞬間に、ここじゃないどこかがどうしても欲しくなるときがある。自転車で1時間かけて登校する道中がなんとなくだるくて、進路について話す同級生を見てはなんとなく焦って、離れた席から聞こえてくる笑い声でなんとなく息苦しくなる。そんな「なんとなく」にフィクションはよく効いた。
少女漫画は未知なる世界
高校時代、少年漫画はもちろん大好きだったけど、同じように少女漫画も大好きだった。ぼくにとっていつも少女漫画は未知なもので、だからこそワクワクした。「友情」「努力」「勝利」というジャンプ三原則的なものとは縁遠い(もちろんそういう少女漫画だってあるけれど)物語たち。敵との闘いよりも、内面の感覚が丁寧に掘り下げられていく。当時好きだった少女漫画作家はたくさんいる。ジョージ朝倉、いくえみ綾、矢沢あい。そのなかでも、特に思い入れが強いのは羽海野チカ『ハチミツとクローバー』だ。

『ハチミツとクローバー』
羽海野チカ(集英社)
自分自身が芸大への進学を考えていたこともあって、漫画のなかで描かれる美大生たちの青春群像劇に「俺もこんな大学生活送りて~!」と心で絶叫しながら読み漁った。まあ、もちろん実際の大学生活はハチクロライフとはかけ離れていたけれど。
羽海野さんの絵はどうしてこんなにも匂いを感じるのだろう。冬の夜の香りや、ホカホカのコロッケの食欲をそそる匂いが、線のひとつひとつにまで染みわたっている。ページの隅々まで青春が香り立っている。そして、読み返すたびに身悶えしてしまうのが、恋に落ちた瞬間を描いたときの鮮やかさ。風が吹き、それまで見えていた景色が一変してしまう瞬間。その輝かしさとせつなさ。ああ、また読みたくなってきた。
言葉の力に感動
舞城王太郎の小説を初めて手にとったときの衝撃は忘れられない。高校1年生、地元の本屋でふと目にとまった『阿修羅ガール』というタイトル。表紙に使われている女子高生が線路を渡る写真も印象的だった。なんとなく手にとって本を開き、目に飛び込んできた書き出し。

『阿修羅ガール』
舞城王太郎(新潮社)
「減るもんじゃねーだろとか言われたのでとりあえずやってみたらちゃんと減った。私の自尊心。返せ」
いままで自分が読んできた小説とは明らかに違う。語感もリズムも熱も、圧倒的に新しかった。ソッコーで買って、無我夢中になって読み終えた。奇想天外な物語にも驚いたけれど、それ以上に言葉の力に感動した。言葉ってこんなに気持ちいいんだ。言葉ってこんなに自由なんだ。自分のなかのどこかの蓋がパカっと開くのがわかった。いつもなにかに怯えているような学生生活だったけれど、舞城王太郎と出会えたおかげで、ぼくはほんの少したくましくなれた。
『阿修羅ガール』を読み終えたぼくは、すぐさま他の舞城作品も買い漁り、時間も忘れて読みふけった。そして、新刊を待つのが人生の楽しみになって、いざ発売されたら秒で買って徹夜で読んだ。そんな熱烈な舞城ファンになったぼくは、だんだんと「どうやら舞城王太郎は海外文学の影響も受けてるぽいぞ」と気づき始め、アメリカ文学や南米文学も読み始めるようになる。
学生時代に読んだ海外文学で最も記憶に残ってるのはイアン・マキューアン『贖罪』だ。

『贖罪』
イアン・マキューアン(新潮文庫)
海外文学は値段が張るので、図書室にリクエストを出してなんとか読むことができた。ぶ厚いハードカバーに最初はたじろいだけれど、読み始めたらページをめくる手が止まらなかった。これは物語についての物語で、物語の持つ力の美しさと怖さ両方がパラメータマックスで書かれていた。
ぼくは、いま物語を書く仕事をしている。そんなぼくの背骨になっているのは、ずっとイアン・マキューアンの『贖罪』だ。
三浦直之
ロロ主宰/劇作家/演出家。1987年宮城県生まれ。2009年劇団ロロを設立。全作品の脚本・演出を担当するほか、舞台演出、脚本などで幅広く活動する。15年から高校演劇のルールに沿った60分の連作群像劇「いつ高シリーズ」を始動。
ロロ official http://loloweb.jp/
イラスト:くぼあやこ
※この記事は『ETHICS for YOUTH』2023年夏号(No.2)に掲載したものです。