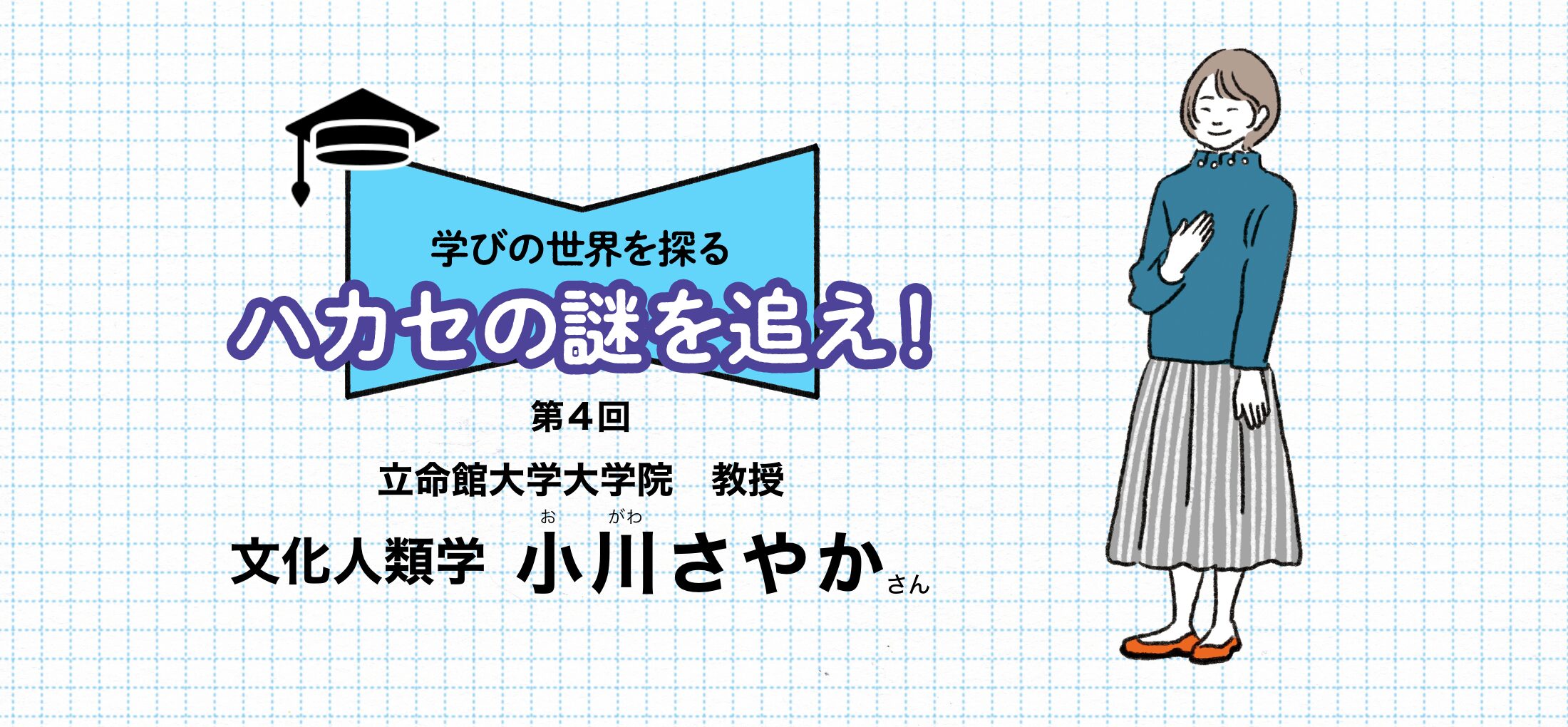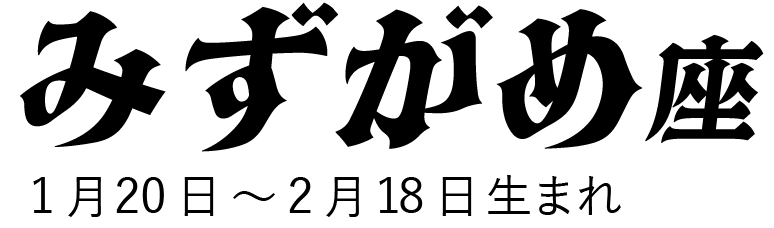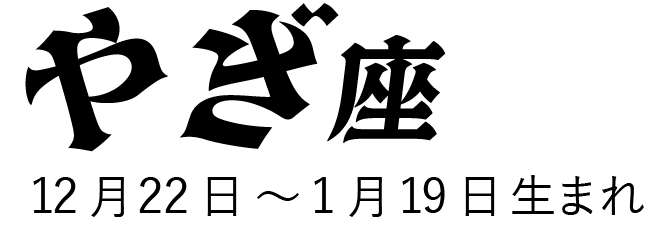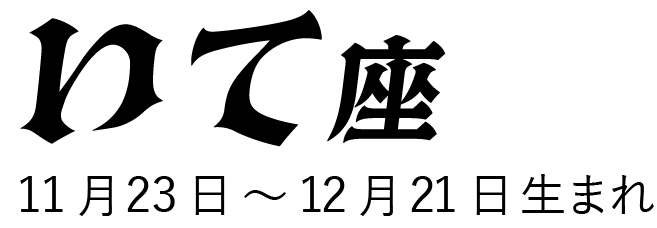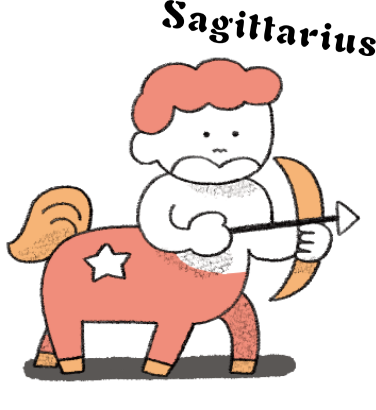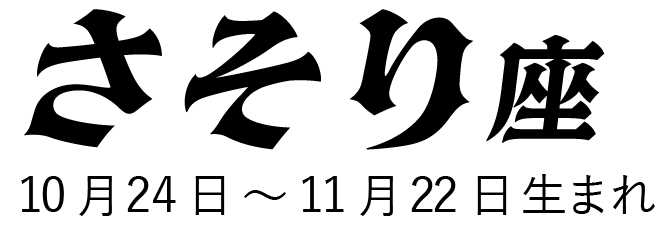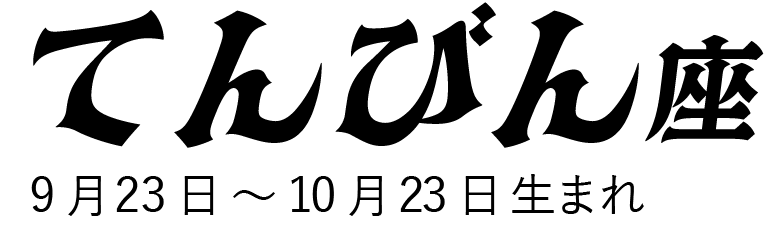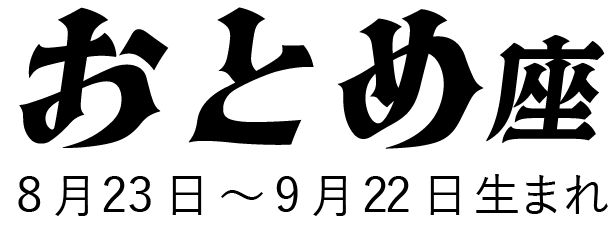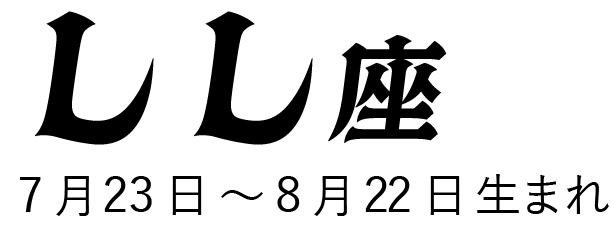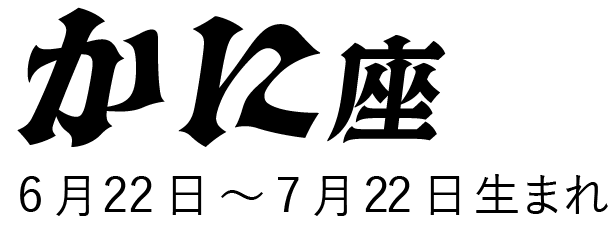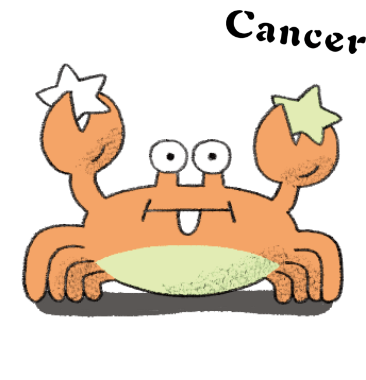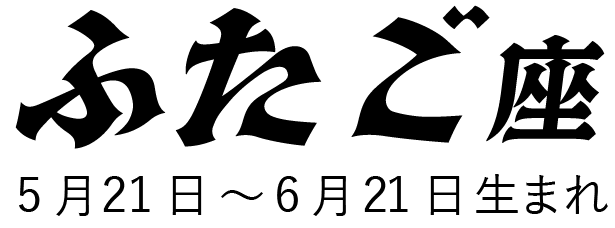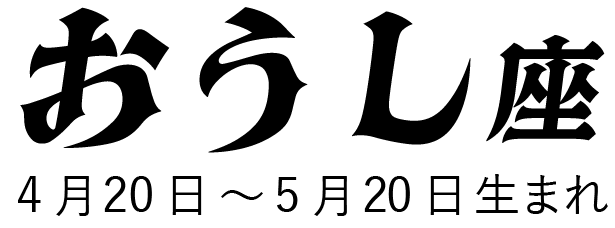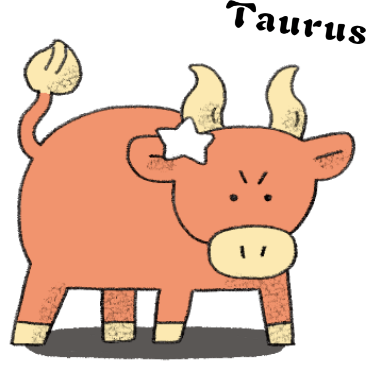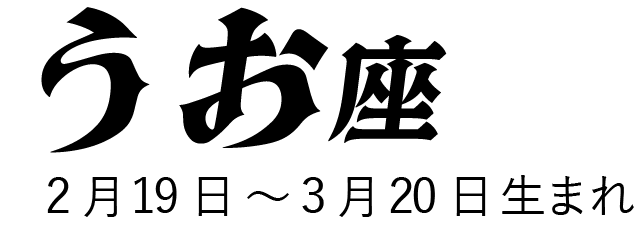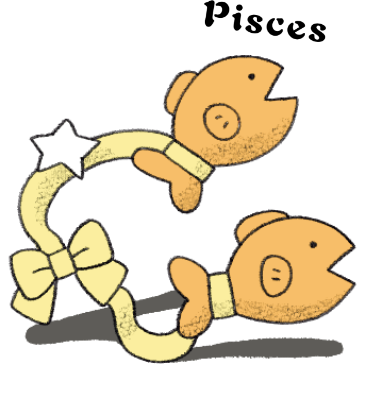生活を共にし、考える
「文化人類学って異文化の研究なんですか?」と、よく聞かれます。確かに文化人類学のフィールドワークは、今自分がいるところとは、異なる世界で調査をします。しかし、目的は異文化を知ることだけではありません。
現地の人と生活をすることで、自分たちが当たり前と思っていたことがそうではなかったことに気づき、自分たちの社会の問題についても考えるようになります。同時代を生きる異文化の人たちと、互いの違いや共通性を語り合う。そこから「こんな世界もいいね」と未来を一緒に考えるのは、とても楽しい体験です。
タンザニアの路上で古着売り
大学生の時、海外でバックパッカーをするうちに、現地の人ともっと関わりたい、いっそ住んでみたいと思うようになりました。それが私の文化人類学への入り口でした。大学院でフィールドワークの地に選んだのはアフリカのタンザニアです。偶然知り合った現地の路上商人と一緒に3、4年ほど路上で古着を売って暮らしました。
タンザニアの商人たちと生活を共にしてみて、日本人との考え方や生き方の違いにたくさん気づきました。社会保障制度もなく収入も不安定なタンザニアでは、何かあっても生きていけるように、みんな一人で何十もの仕事を持っています。
商売でも、騙したり騙されたり、気前よくまけたりするので、お客との間に「貸し借り」が生まれます。ただ、彼らは「貸し」をつくってもお返しは期待しません。人に何かを与えたり、助けたりすることで、相手に「借り」を残しておくようにします。この「借り」が、相手と一生にわたるつながりをつくっていくのです。

行商人仲間と(2004年)

定期市で(2005年)
この「借り」を私は「人間貯金」と呼んでいます。だから彼らは、貯金はゼロでも人間貯金がたくさん。ピンチの時に思い浮かぶ顔、頼れる人がいるのです。
多様性は自分の中に持つもの
彼らと現地で生活をし、「多様性」の本当の意味も分かりました。
タンザニアの人は、自分と異なる人と関係をつくるのがとても上手です。受け入れられない考え方や行動はありましたが、理解はできなくても、つきあってみることはできる。「そういう考え方もあるのか」と気づいたり考えたり、疑問を持ったりした時に、聞いたり調べたりすることが、その人の人生を豊かにしてくれます。
多様性とは受け入れるべき倫理や道徳ではなく、自分の中に持つもの。多様な人間関係を持っていれば、自分とは違うアイデアをもらえる。世界が多様で、私たちが分かり合えない者同士であればあるほど、うまくいかなくなった時に、あなたを受け入れてくれる場所が増えるのです。

ふるまう豆料理の準備をしているところ
異なる人と関わってみる
文化人類学は海外に行かないとできないわけではありません。異なった人たちは身近にたくさんいます。例えば何の話をしても全部数値で書いている数学者なんて異なった人ですよね。どんな思考回路でやっているのか、彼らの毎日を研究したっていい。時間を共にしていると、ゆっくりでも相手のことが分かってきます。そういう体験をしているうちに「新しい私」が生まれてくる驚きがありますね。そこが文化人類学の面白さかもしれません。
「文化人類学」とは
人々の文化や習慣を研究する学問です。異なる国や地域の人々がどのように生活し、考え、行動するかを調べ、それを理解しようとします。実際に研究対象となる現地に行き、現地の言葉を習得し、一緒に生活しながら人々の生活を観察したり、インタビューをしたりして、調査し、研究します。これを「フィールドワーク」と言います。

小中高生時代
読書、空想、創作好き。「ここではないどこか」に思いをはせる子供だった。
大学時代
信州大学人文学部に進学。ワンダーフォーゲル部で登山をしたり、バックパッカーで世界を回る。1年時の講義で文化人類学に惹かれ、学び始める。
大学院時代
フィールドワークでタンザニアに渡る。路上商人に魅力を感じ調査開始。のちに調査助手兼友人となるロバートと出会い、古着の行商を一緒に始める。
立命館大学の教授に
40歳で教授となり、指導、研究、執筆と「スーパー忙しい」毎日。タンザニア人の「借り」をつくりながら経済を回す仕組みや、香港に渡ったタンザニア人たちの交易に関する研究に取り組む。


「贈り物」の話
「贈り物」は人間関係を変える
「友だちから1000円のプレゼントをもらったら、いくらくらいのプレゼントを返しますか?」
そう聞くと、多くの人は「同じくらいの物」と答えます。同じくらいの値段の物を買うんだったら、最初から自分で好きな物を買った方がいい。なぜ、わざわざ同じくらいの物を返すのでしょう。
それは、「同じくらいの物を返す」ことで、「私たちは対等な友だちだよね」ということを確認しているから。
自分が1000円のプレゼントをして、友だちから10万円のバッグが返ってきたら、どう思いますか?お金を持っていることを自慢され、マウンティングをされたような気持ちになってしまうかもしれません。友だち同士の「対等性」が失われてしまうからです。
友だちではなく、先生にプレゼントをして、先生から同じくらいの物が返ってきたらどうでしょう。ちょっとケチくさい感じがしませんか?
友だち同士とは違って、生徒と教師は対等ではありません。そのことを知っているから、自分がちょっと贈り物をすれば、先生はもっといいものをくれると期待してしまうというわけです。
それは、誰かに助けてもらったり、何かをしてもらうことも同じです。常に友だちに助けてもらってばかりいると、その人に頭が上がらないような気分になって、やがてそこに上下関係が生まれ、自分が精神的に下の立場になっているような感覚になってしまうこともあります。
このように、「贈り物」は人と人との関係性を変えてしまうこともあります。「贈り物」っていいものだと思いがちですが、とても難しいんです。
そんなことにならないようにするには、「前にちょっとしたものをプレゼントしたから、何かあった時には助けてもらえそう」くらいの気持ちで「贈る」と「返す」を回していくこと。そうすると、一方に負い目を感じさせることもないし、人間関係が楽しくなると思います。「贈り物」は、人間関係を調整する物でもあるのです。
「贈り物」は与え手の元に帰りたい?
フランスの文化人類学者にマルセル・モースという人がいます。モースが書いた『贈与論』という本には、ニュージーランドの先住民族・マオリ族の話が出てきます。
マオリ族の人たちは、贈り物には与え手の霊が憑いていると考えています。そして、贈った物は、与えた人の元に帰りたいと思っている。だから「お返し」が起きるのだというのです。
オカルトのような話に聞こえるかもしれませんが、身に覚えがありませんか?
例えば、好きではない人から手編みのマフラーをもらって負担に感じたり、人からもらったプレゼントを別の人に売るのが心苦しかったりしたことはありませんか。そう感じるのも、そこに贈り手の何かが付いていると思うからではないでしょうか。
贈り物が人生に影響を与えることもあります。フィールドワークをしたタンザニアで、ある青年からこんな話を聞きました。
青年は木材の小売業に失敗し、木材問屋の女性に「掛け売りにしてもらえないか」と相談をしました。すると女性は、「あなたは口下手で商売には向いていないけど、職人になって成功した亡くなった甥にそっくり。あなたも職人になったら?」と、甥の遺品だったカンナやノコギリを青年にくれたのです。
青年は、独立して家具職人を始めました。そして「道具を磨いていると、彼女のことを思い出す。いつか立派な職人になったら彼女にお返ししたい」と言っていました。
彼が立派な職人になれるかどうかは未知数ですが、彼がカンナやノコギリに付いている木材問屋の女性と一緒に生きているのは事実。与え手は贈った物に、「立派な職人になってね」とか「しっかり自立してね」といった思いや圧を乗せている。もらった青年は、贈り物にお返しをするまで、その贈り物の分身と一緒に生きているわけです。
私たちが、家族の形見を身に着けていると悪いことはできないというのと同じような感情。送り物を通して、人はその人の人生に影響を与えることができるのです。
でも、贈り物は毒にもなります。
マオリ族の言葉では、贈り物に憑く霊のことを「ハウ」といいます。ハウが動詞になると「煽動する」「鼓舞する」や「台なしにする」「破壊する」という意味になります。
例えば、あまりに豪華な勉強キットを親からもらって、すっかり勉強をするのが嫌になってしまったということも起こるわけです。
私たちは贈り物を通じて、社会をつくり、人をつくっている。皆さんにはそんなことを考えてもらいたいと思います。
小川さやか
小川さやか
1978年愛知県生まれ。専門は文化人類学、アフリカ研究。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程指導認定退学。博士(地域研究)。国立民族学博物館研究戦略センター機関センター助教、立命館大学大学院先端総合学術研究科准教授などを経て現職。著書に『都市を生きぬくための狡知―タンザニアの零細商人マチンガの民族誌』、『チョンキンマンションのボスは知っている―アングラ経済の人類学』。河合隼雄学芸賞など受賞歴多数。

イラスト:くぼあやこ
※この記事は『ETHICS for YOUTH』2023-24年冬号(No.4)に掲載したものです。
※コラムはウェブオリジナルです。